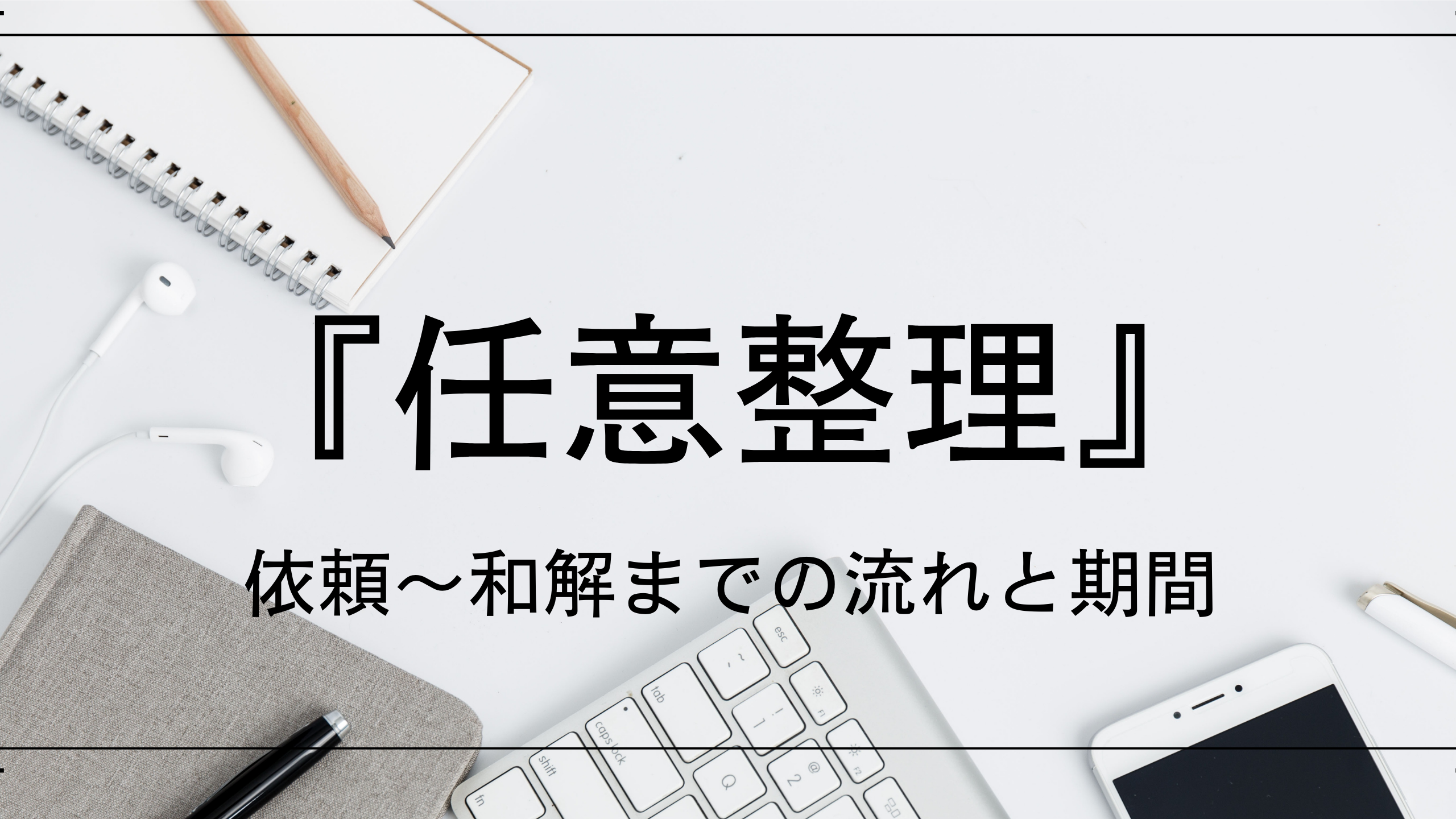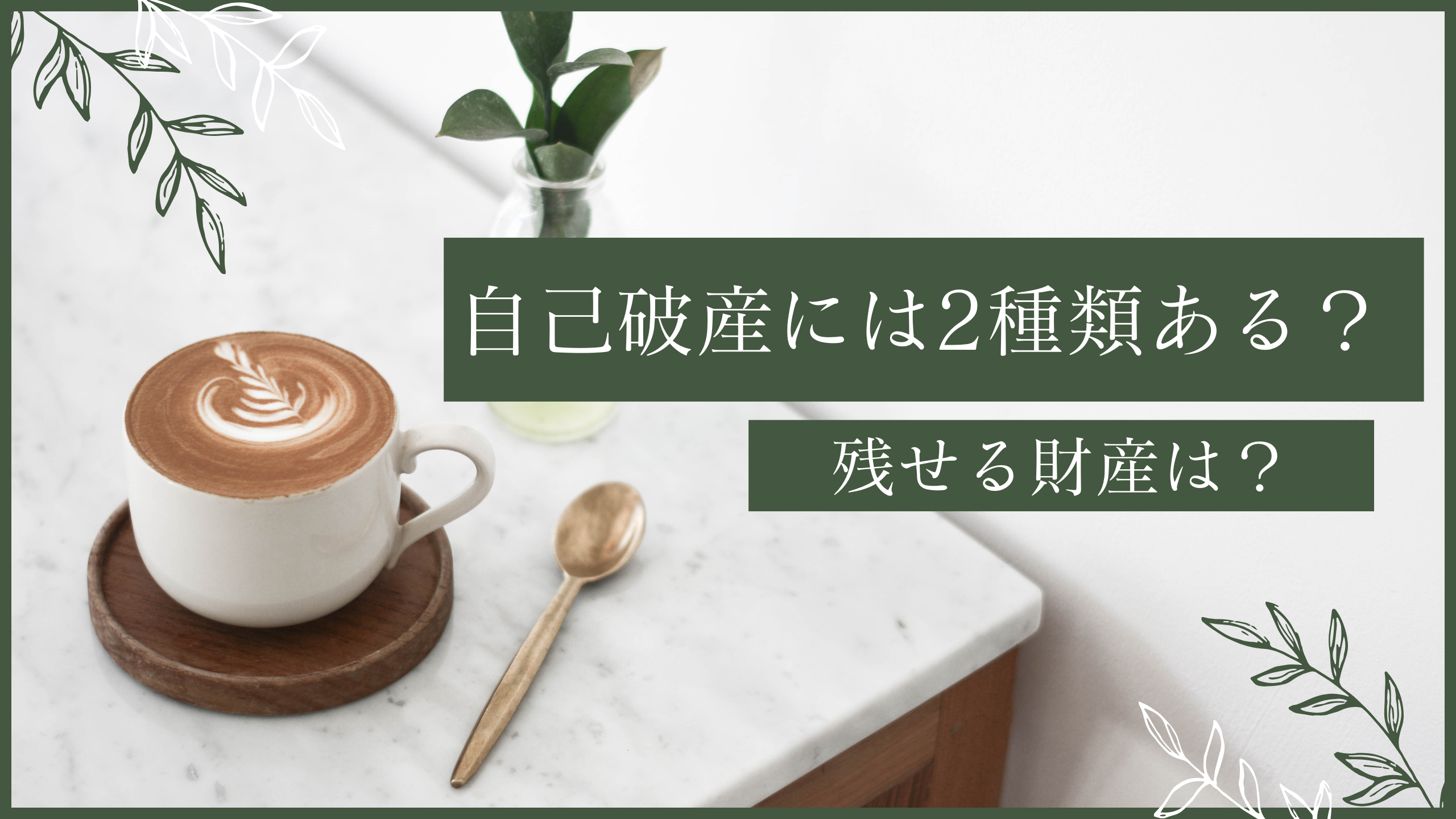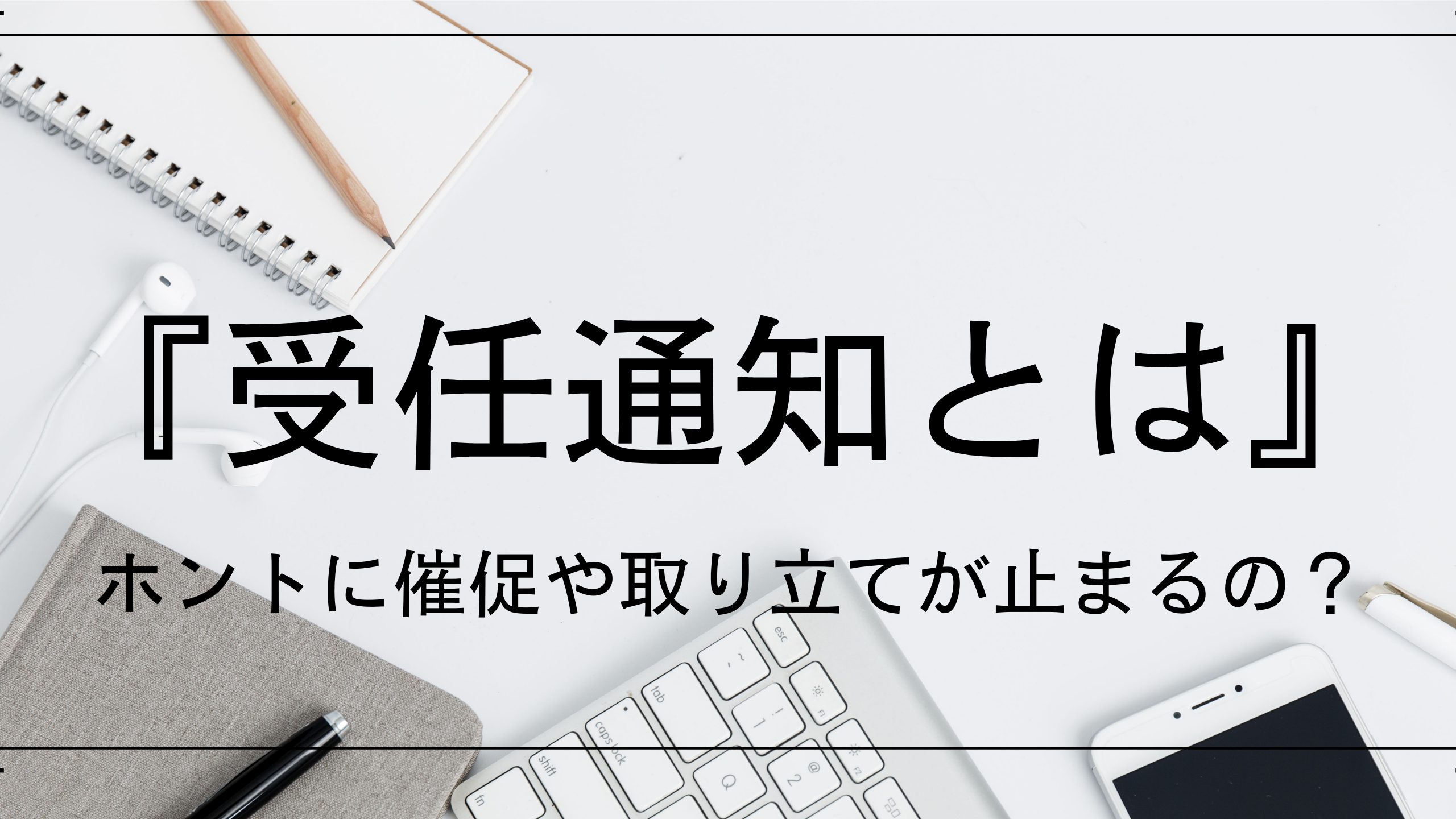この記事では、任意整理を検討している方に向けて、実際の流れや気をつけるべきポイントまでを網羅的に解説します。
【目次】
① 任意整理とは?
任意整理は、借金の返済が困難になった際に弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来の利息や延滞金をカットしてもらい、元金ベースで返済していく手続きです。
裁判所を通さない私的整理なので、比較的早く進めやすく、家族や職場に知られにくいというメリットもあります。
② 弁護士・司法書士への無料相談と受任まで
まずは弁護士事務所や司法書士事務所に無料相談を申し込みます。
- 相談時には多くの場合、最初は事務スタッフがヒアリングを担当します。
- 事務員だけで話が進むこともありますが、日本弁護士連合会(日弁連)の規定により、正式な「受任」には弁護士との面談が必要です。
相談内容に問題がなければ、その場で「任意整理を依頼(受任)」となり、契約書の締結に進みます。
債務整理・自己破産などの問題は弁護士法人ひばり法律事務所が解決
③ 受任通知の送付とその効果
受任が決まると、弁護士は各債権者に「受任通知」を送付します。
◆ 受任通知とは?
これは「この債務者の債務整理を弁護士が受任しました」という正式な通知であり、貸金業法に基づき債権者は督促や取立てを中止しなければなりません。
注意点:
受任通知が届いても手続き上、口座引き落としがすぐには止まらない場合があるため、生活費などが必要な場合は事前に引き出しておくなど対策が必要です。
④ 債務調査と引き直し計算とは?
各債権者から取引履歴が送られてきたら、利息制限法に基づいて「引き直し計算」を行います。
◆ 引き直し計算とは?
法定金利(上限年15〜20%)を超える利息で取引していた場合、本来の返済額を再計算し、過払い金が発生している可能性を確認する作業です。
この作業を通して、実際に返済すべき元本が確定します。
⑤ 和解交渉と成立までの流れ
引き直し後の債務総額が確定したら、弁護士が債権者と「元金ベースでの分割返済」の交渉を行います。
- 将来利息・遅延損害金はカット
- 返済期間は一般的に3〜5年(36〜60回)
- 債権者が複数ある場合、和解条件や返済回数が各社で異なることもあります
◆ 弁護士費用の支払いについて
- 事務所によっては、和解交渉中に弁護士費用を分割で支払うケースも
- この支払い実績を通じて、「債務者に継続的な支払い能力があるか」も見極めている側面があります
- 着手金を支払わなければ手続きが始まらないという事務所もありますので、事前に確認が必要です
◆ 和解成立までの期間
受任から和解成立までは通常3〜6ヶ月。ただし業者によっては時間がかかる場合もあります。
注意:
まれに、和解までの間に法的手段(訴訟・差押え)に出てくる債権者も存在します。早めに受任することでリスクは回避しやすくなります。
⑥ 返済の開始と完済まで
和解が成立すれば、そこから毎月の返済がスタートします。
◆ 誰が返済するの?
- 返済方法は2パターンあります:
- 債務者本人が各社に直接振込
- 弁護士事務所が集金・送金を代行(手数料がかかることも)
◆ 返済完了までの目安
3〜5年の分割返済が一般的。途中で返済不能にならないよう、家計管理が重要になります。
● 家族・勤務先
任意整理は裁判所を通さないため、原則的にバレることはありませんが、郵送物や家族カードなどには注意が必要です。
次回の記事予告
- 任意整理中の生活費のやりくり術
- 家族にどう説明する?任意整理のリアル
- 弁護士費用を抑えるコツと相場比較