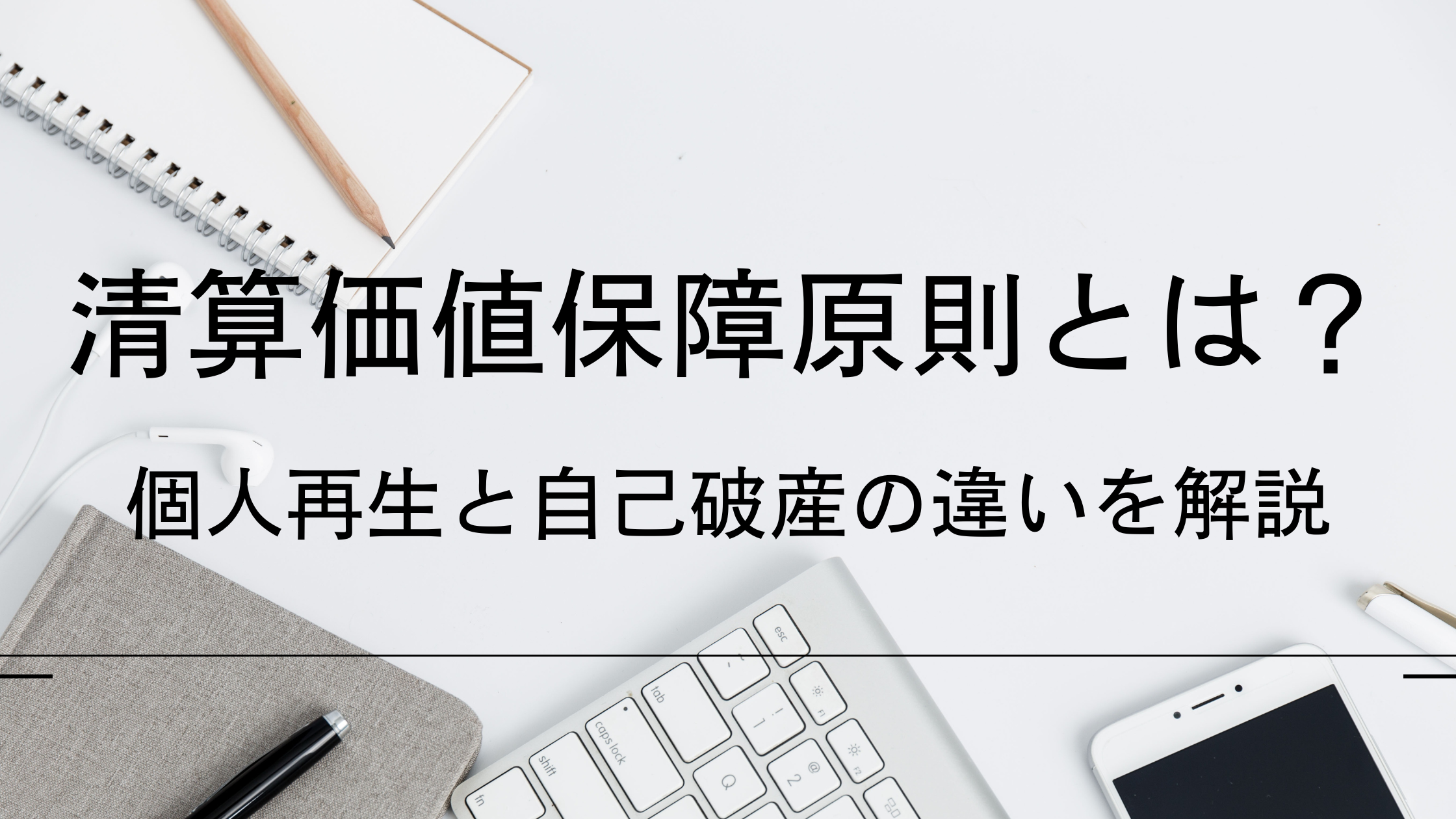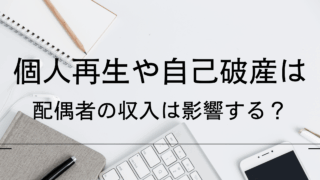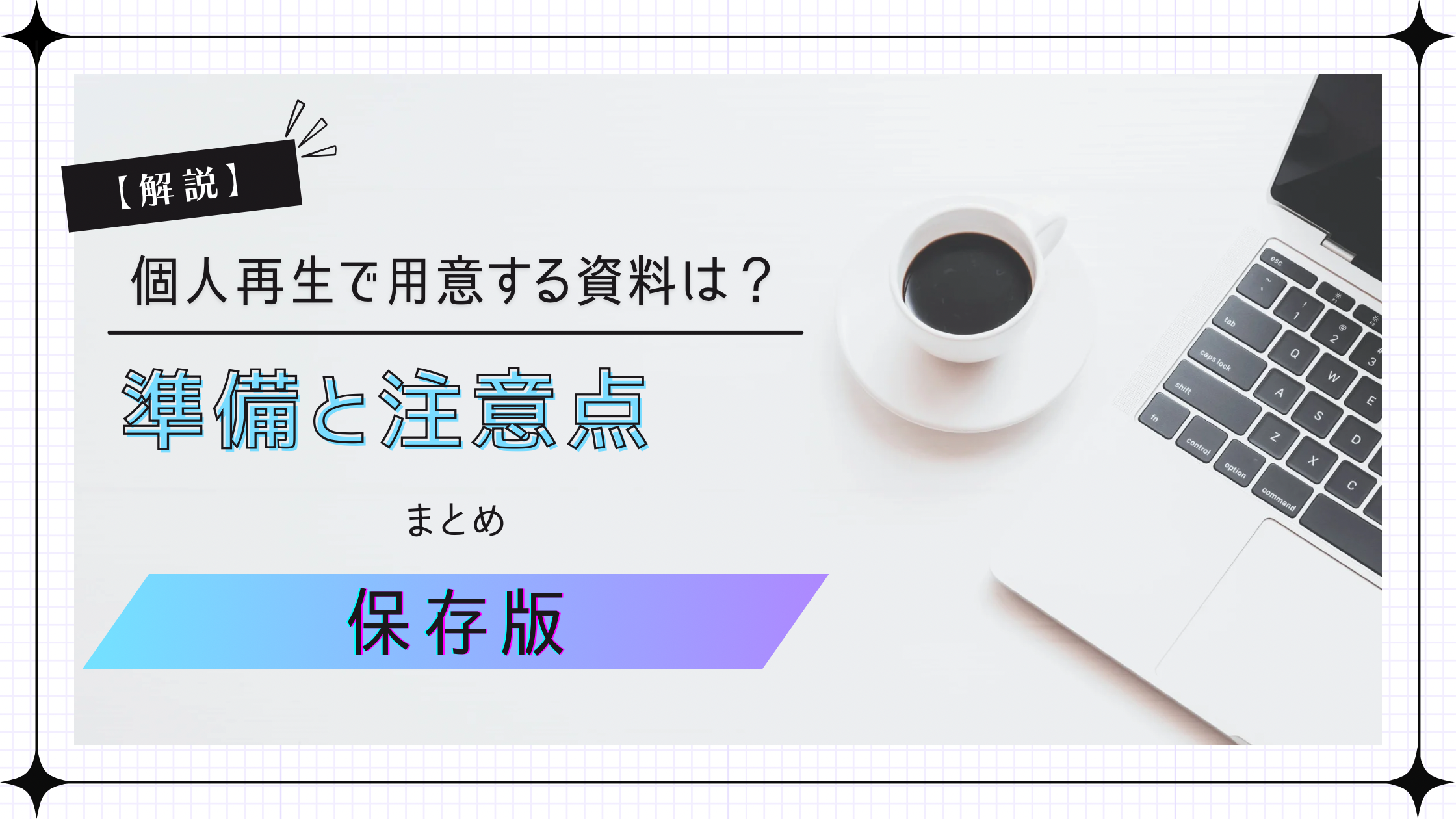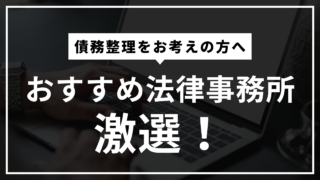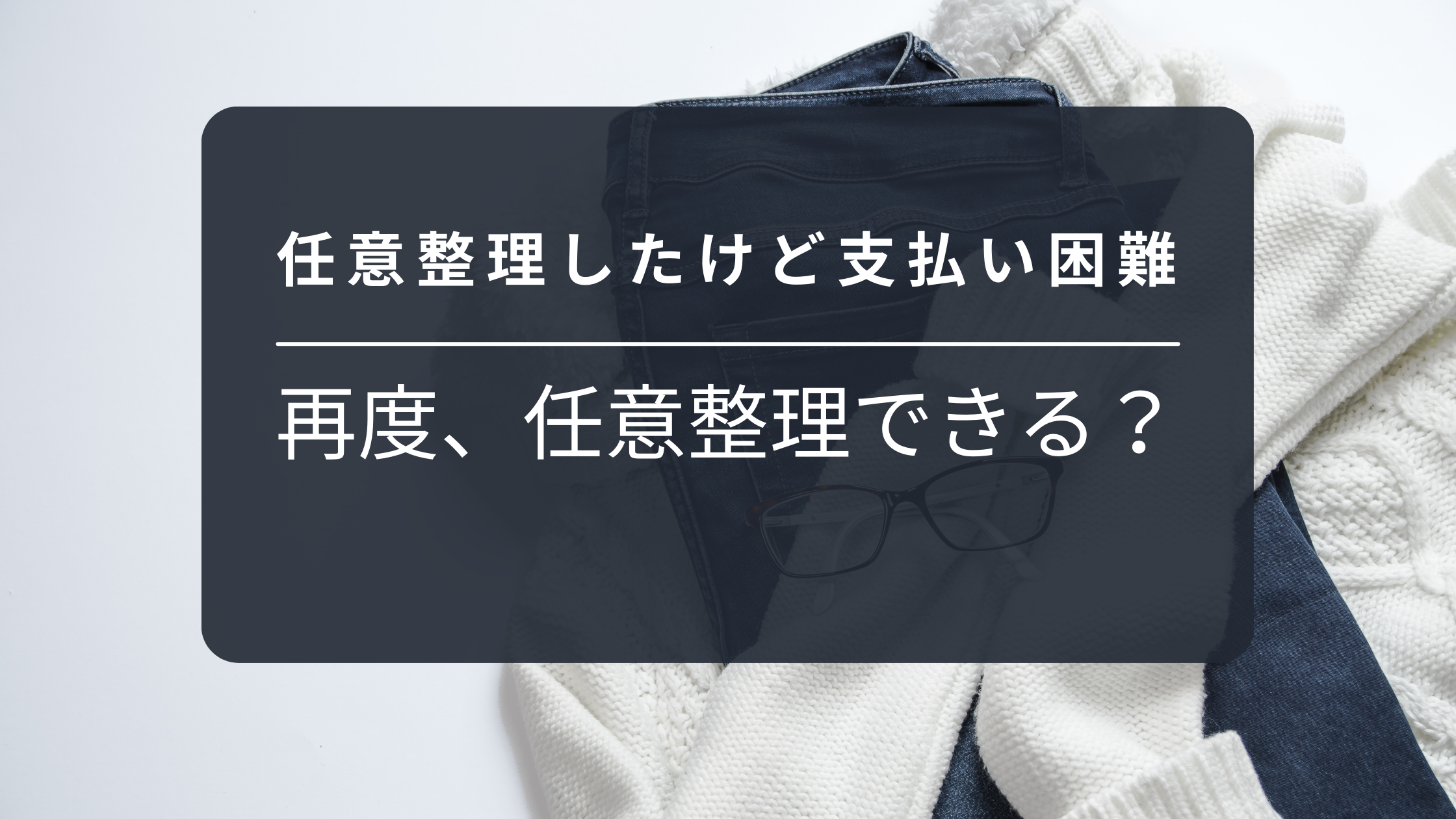【図解でわかる】清算価値保障原則とは?自己破産と個人再生の違いを徹底比較!
借金の整理を考える中で、自己破産と個人再生の違いに迷う方も多いはずです。
その中でも、個人再生で特に重要となるのが「清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく)」という考え方です。
この記事では、清算価値保障原則の基本と、自己破産との違い、そして注意点を専門家目線でわかりやすく解説します。
清算価値保障原則とは?
清算価値保障原則とは、個人再生の返済額は、自己破産をした場合に債権者が受け取れる金額以上でなければならないという原則です。
つまり、あなたが持っている財産のうち「自己破産をすれば処分されるはずの価値」を最低限、個人再生では返済に回す必要があるのです。
例:財産のある人のケース
- 自己破産 → 車・預貯金などの財産が処分される
- 個人再生 → これらの財産を維持できる代わりに、その価値分は3~5年間で返済する必要がある
財産が多い人ほど、個人再生の返済額が高くなるという仕組みです。
自己破産と個人再生の違い
| 項目 | 自己破産 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 裁判所の手続き | あり | あり |
| 借金の免除 | ほぼ全額免除 | 一部返済(5分の1など) |
| 財産の処分 | 原則すべて処分 | 処分されないが、価値分は返済に反映 |
| 官報掲載 | あり | あり |
| 資格制限 | 一部制限あり(職業制限) | なし |
| 住宅の維持 | 原則不可 | 可(住宅資金特別条項あり) |
清算価値に含まれる財産とは?
主に以下のような財産が「清算価値」の対象になります。
- 現金・預貯金
- 自動車・バイク
- 生命保険の解約返戻金
- 株・投資信託
- 不動産(住宅ローン対象含む)
- 退職金(見込み額の8分の1〜4分の1程度)
清算価値の算定には専門的な判断が必要です。
法律事務所では、弁護士がこれらを詳細に評価し、再生計画を立てます。
清算価値保障原則により返済額が増えるケース
個人再生では、以下のような人が返済額の増加リスクを抱えやすいです。
- 高額な解約返戻金付き保険に加入している
- 車の市場価値が高い(ローンなし)
- 持ち家にある程度の資産価値がある
- 退職金見込額が高額
逆に、財産がほとんどない人は最低弁済額(原則100万円〜)になることが多いです。
まとめ:自己破産か個人再生か、財産状況がカギ
清算価値保障原則は、個人再生を考えるうえで避けては通れないルールです。
自宅や車を守りたい人には個人再生が向いていますが、財産が少なく安定収入がなければ、自己破産の方が早く立ち直れることもあります。
いずれにしても、弁護士や司法書士とよく相談し、財産と返済能力に合った債務整理方法を選ぶことが重要です。