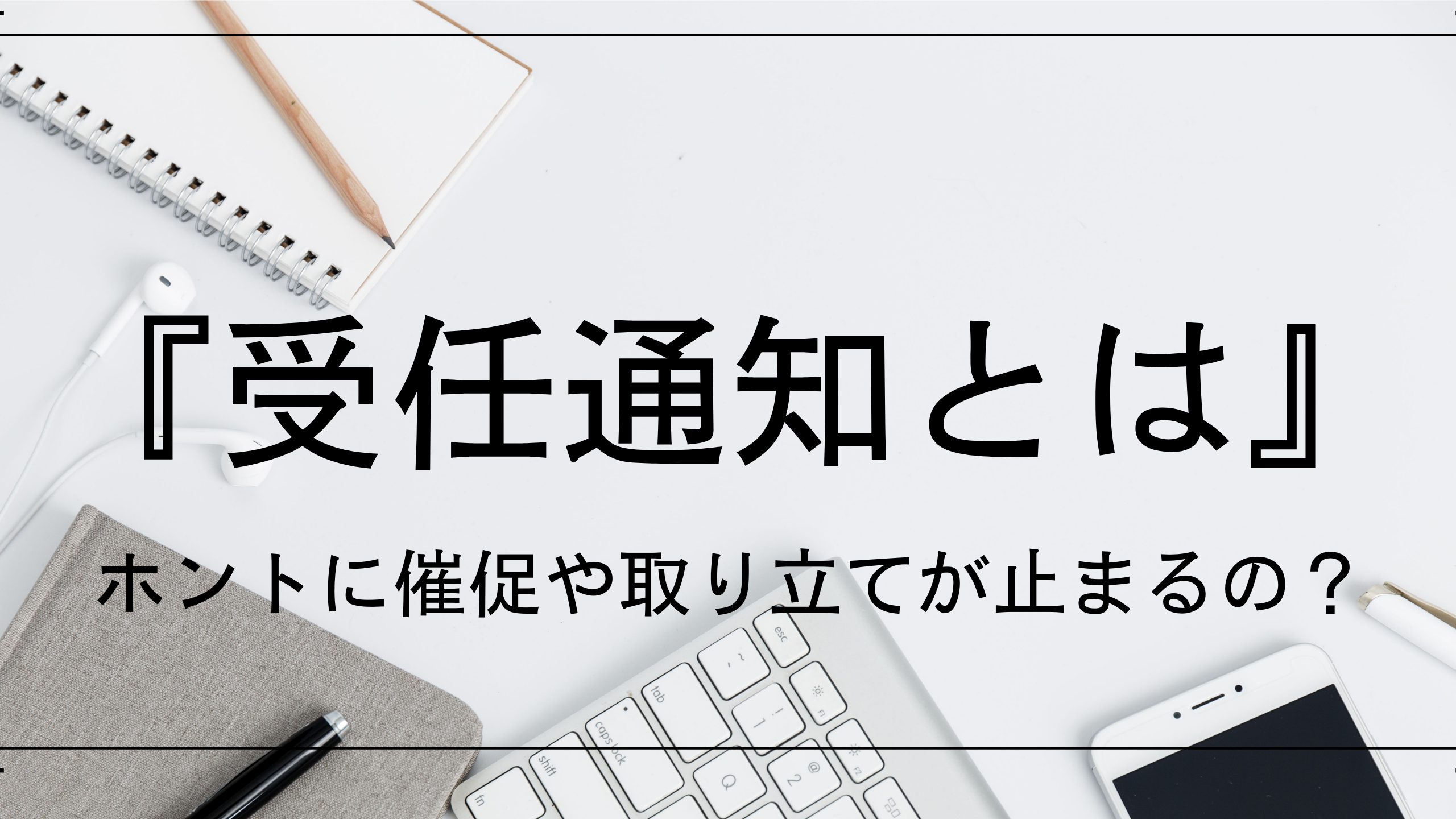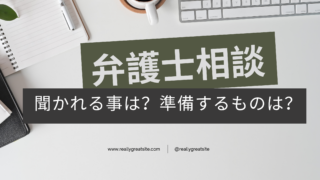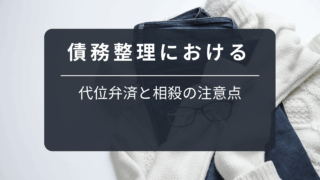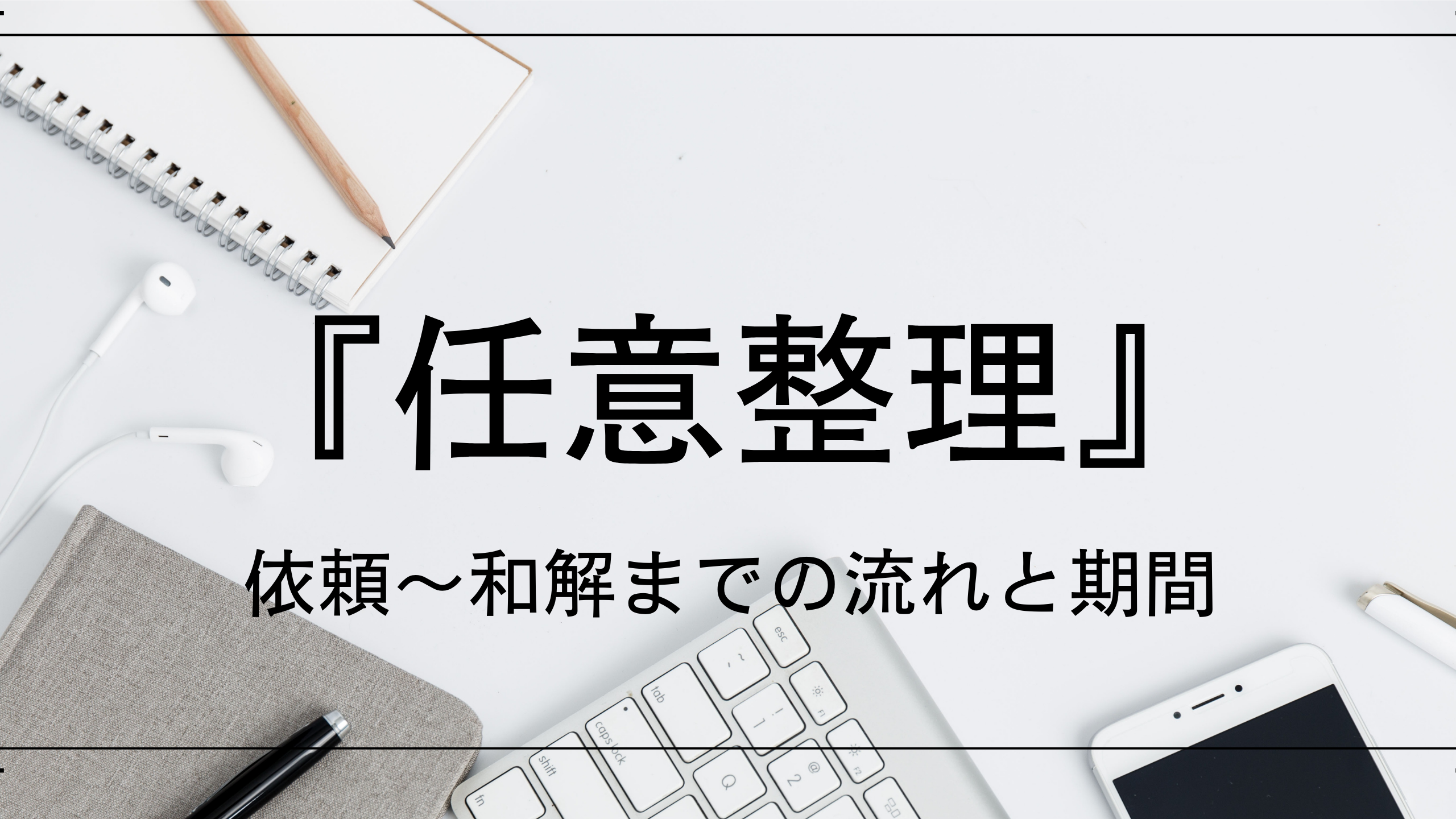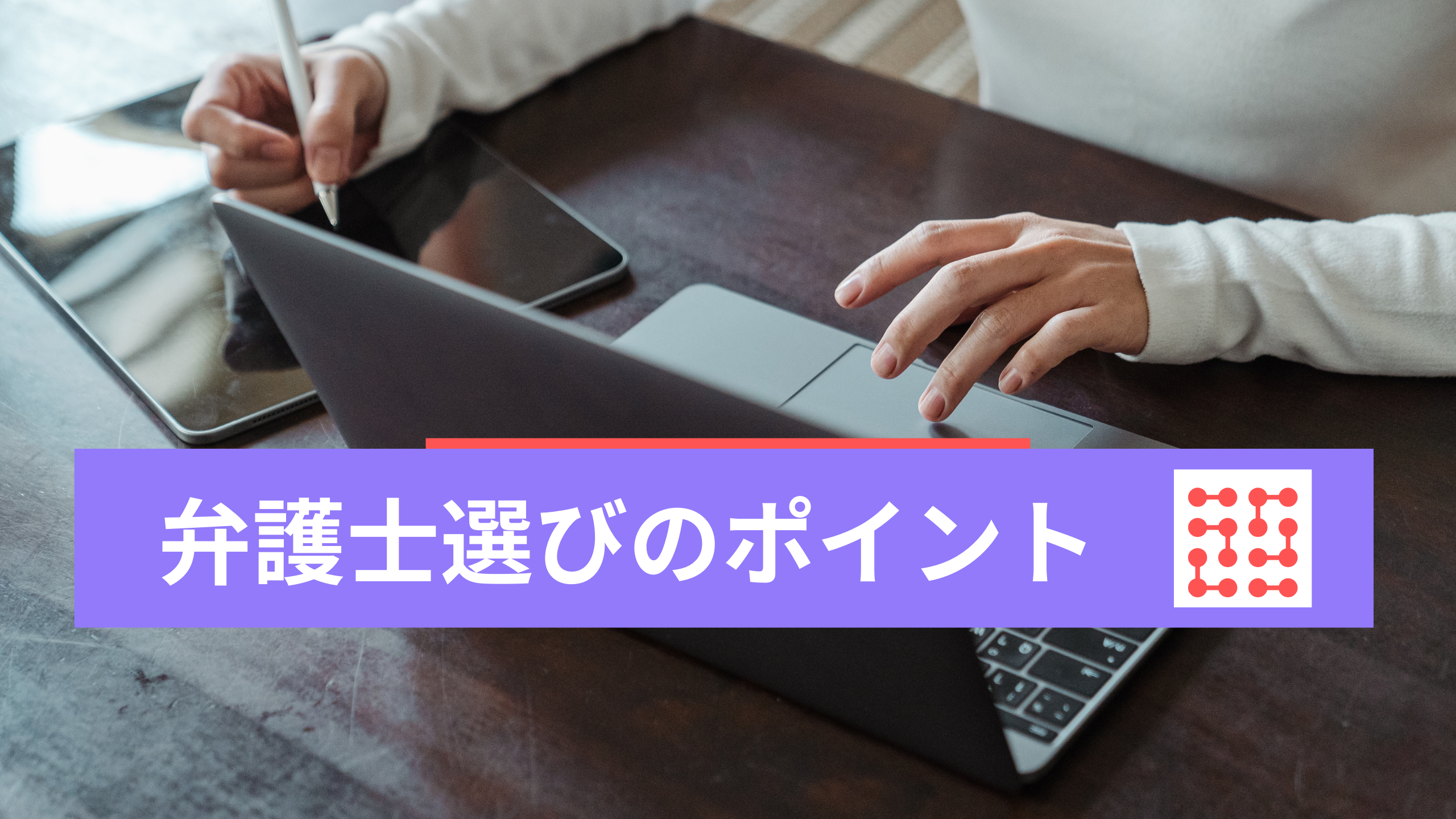借金の返済に限界を感じ、「債務整理をしようか悩んでいる」という方の多くが気になるのが「受任通知」です。
今回は、弁護士・司法書士が送る受任通知の効果や、できなくなることについて、借金に悩む方の立場に寄り添ってわかりやすく解説します。
【目次】
- 受任通知とは?
- 受任通知でできなくなること
- 受任通知の効力の範囲
- すでに訴訟や差押えが起こされている場合は?
- 社会保険料・公共料金・奨学金はどうなる?
- なぜ催促が止まるのか?
- 保証人がついている場合の注意点
- 信用情報(ブラックリスト)への影響
- 銀行口座・クレジットカードへの影響
- 困ったときの対応策
受任通知とは?
弁護士または司法書士が債務整理を正式に受けた際、債権者に対して送る通知です。
通知が送られることで、貸金業者は法的に取り立てや催促をしてはいけなくなります(貸金業法第21条)。
受任通知でできなくなること
- 電話や郵送での取り立て
- 勤務先への連絡
- 一方的な返済の催促
- 新たな利息・遅延損害金の発生
受任通知が届いた瞬間から、これらの行為は禁止されます。
受任通知の効力の範囲
効力が及ぶのは「通知を送った債権者のみ」です。
- 全ての債権者に通知を送る必要があります
- 通知を出していない業者には、催促や請求が続く可能性があります
すでに訴訟・差押えが起こされている場合は?
受任通知は「将来の取り立てを止める効果」はありますが、訴訟や差押えがすでに始まっている場合は効力が及びません。
この場合は、弁護士が個別に対応を検討します。
社会保険料・公共料金・奨学金はどうなる?
任意整理では、債権者(貸金業者やクレジット会社)との和解が対象です。
以下のような支払いは任意整理の対象外です:
- 社会保険料
- 公共料金(水道・電気・ガス)
- 税金
- 日本学生支援機構などの奨学金(保証人がついている場合)
これらの支払いは、そのまま続ける必要があります。
なぜ催促が止まるのか?
理由は法律によって決まっています。
貸金業法第21条1項9号では、債務整理を受任した弁護士・司法書士が受任通知を送ることで、債権者による取り立て行為は禁止されると明記されています。
保証人がついている場合は?
主債務者が任意整理をしても、保証人には受任通知は送られません。
そのため、保証人に対して督促がいく可能性があります。
家族や親族が保証人になっている場合は、事前に相談・説明しておくことが重要です。
信用情報(ブラックリスト)への影響
受任通知が送られると、その情報は信用情報機関に登録されます(事故情報)。
つまり「ブラックリスト入り」となり、新たな借入・クレジットカードの利用が制限されます。
登録期間は次の通りです:
- CIC、JICC:完済から5年
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):最長10年
銀行口座やクレジットカードはどうなる?
◆ 銀行口座の凍結について
任意整理の対象に銀行カードローンやクレカが含まれている場合、その銀行口座が凍結される可能性があります。その際に銀行口座に預金残高があれば借金の回収として相殺されます。
他の銀行口座については凍結は行われません。
また凍結された口座にも一定期間で利用できるようになります。
例:みずほ銀行のカードローンを任意整理→みずほ銀行の口座が利用停止
◆ 任意整理対象外のクレジットカードは?
任意整理しなかったクレジットカードも、信用情報が共有されて利用停止になる可能性があります。
ただし、すぐに使えなくわけではなく更新時期や定期的な信用情報の確認時のため数ヶ月使える事が多いです。また任意整理の影響が出ないケースも存在するため、個別に確認が必要です。
不安なときの対応方法
- 事前に弁護士・司法書士に質問リストを作って相談
- 催促が来ている場合は、すぐに受任通知を出してもらう
- 保証人がいる場合は、早めに状況を共有
何より大切なのは、一人で悩まず専門家に相談することです。借金問題は、正しく対処すれば必ず前に進めます。
債務整理に強い法律事務所に無料相談する
まとめ
受任通知は、債務整理においてあなたを守る最初の一歩です。
「怖い取り立てが止まる」「支払いの見直しが始まる」など、大きな安心につながる手続きです。
借金に悩む方が少しでも前向きになれるよう、ぜひこの情報を参考にしてください。
次回予告
- 任意整理後の生活に必要な準備
- 支払いが始まる前に見直すべき家計管理術